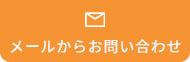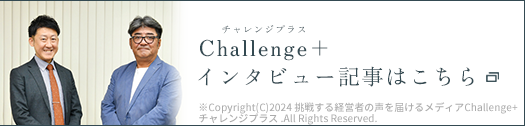相続放棄について
相続に関する問題は、多くの家庭で発生する可能性があるものです。特に相続放棄は複雑な法律的な手続きであり、正しい知識が求められます。相続放棄の順位やその効果と影響、さらに相続放棄後の管理面の問題をきちんと知った上で検討する必要があります。
相続放棄とは、被相続人が残した相続財産を受け取る権利の一切合切を放棄する手続きです。一般的に相続人は被相続人からの財産を受け取る権利を有しますが、同時に負債も承継することになります。負債がある場合は相続放棄を選択することで負債を回避し、相続人としての責任を免れることができます。
相続放棄は家庭裁判所に申立てを行うことによって成立します。原則的な期限としては、被相続人の死亡の事実と自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると「単純承認」といって、相続を承認したものと見なされるため、申立てまでのスピードが非常に重要です。
相続放棄の手続きは、次のような流れになります。
1. **相続人の確定** 初めに、相続人を確定させる必要があります。相続人となる権利がある者が誰かを特定しておきましょう。
2. **財産の確認** 次に、被相続人が残した財産及び負債の状況を確認します。特に負債が多い場合は相続放棄を検討する重要なポイントとなります。
3. **家庭裁判所への申立て** 相続放棄をする場合は家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所への提出書類の準備にも時間を要しますので早めに動く必要があります。
4. **相続放棄の決定** 家庭裁判所が相続放棄を認めれば正式に相続放棄が成立します。この決定後は、元々相続人ではなかったものとみなされます。
相続においては、法律上で定められた相続人の順位があります。第一順位には直系尊属、すなわち子供や孫、第二順位には親や祖父母、第三順位は兄弟姉妹や甥姪が該当します。また、配偶者は常に相続人となります。
相続放棄についても、この法律上の順位にしたがって相続権が次順位の相続人に移っていくことに注意が必要です。
例えば、第一順位である子供が相続放棄を選択した場合、その後は親や祖父母などの第二順位の相続人が相続権を持つことになります。
自分が相続放棄をしたことで負債を免れても、他の親族がその負債をかぶる羽目にあいます。
相続放棄を行う相続人は、次順位の相続人に対してどのような財産と負債が移行するか事前にしっかりと確認し、場合によってはあらかじめそのことを知らせてくおく方が良いでしょう。
相続放棄後は、新たな相続人となる人々が残された財産の管理を行うことになります。この際、管理体制が整っていないとトラブルの原因となります。従って、相続財産が存在する場合には、適切な管理を行うための体制を構築する必要があります。
例えば、不動産や金融資産などが相続財産として残されている場合、適切な管理を行うことにより、その資産の価値を維持することが可能です。そして新しい相続人が正しい事務を行うための引継ぎも重要です。
また相続放棄後であっても、相続財産に関連する行政手続きを行う必要が生じる場合もあります。基本的な法律知識を持つことや、適切な専門家と連携することでしっかりした対応が求められます。
相続放棄は経済的なリスクを回避することを目的として選択されることが一般的です。相続放棄を行うことで想定外の負債を避けることができますし、被相続人が多額の借金をしているなど大きな負債を抱えていた場合には大きな経済的メリットが生まれます。
ただし、全てのケースで最良の選択とは限りません。限定承認という手続きをとった方が良い場合もありますし、安易に相続放棄を選択すべきでなかったと後悔するケースも考えられます。
相続放棄には強力な法的効果があります。相続放棄が承認された場合、その相続人は被相続人の財産や負債に対して何らの権利や義務を負わなくなります。法律上、その相続手続きに関しては、元々相続人ではなかったものとみなされるという重大な効果があります。(手続き上の問題とはいえ、相続人ではないという扱いはさみしいですよね。。。)そして一度その決定がされると特殊なケースでない限りは取消すことができません。それゆえ、相続放棄を決定する場合には慎重かつ迅速な検討が必要です。困った際にはすぐに専門家に相談するようにしてください。