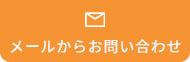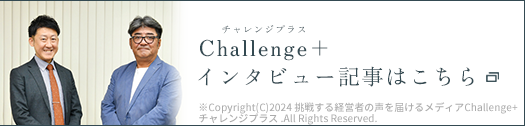贈与の登記と贈与税
不動産の贈与をするにあたっては登記が必要になることと贈与税が発生する可能性があることに注意が必要です。
特に親族間の贈与では、相続時精算課税制度を用いることで適切に贈与を行うことができ、後のトラブルを防ぐことにもつながります。贈与税の基本知識、登記手続きの重要性、親族間の贈与における実務的なポイント、トラブルを避けるための注意点を記載します。
贈与税はその名の通り、贈与が行われた際に課される税金です。親から子供、祖父母から孫への贈与がよく見受けられます。贈与税は、贈与を受けた側が支払わなければなりません。
税金の計算方法は贈与財産の評価額に応じて異なります。ただし、一般的には贈与された財産の価値が110万円までは非課税となります。このため贈与税の課税対象となる金額は、贈与額からこの基礎控除である110万円を引いた金額になります。
そして、贈与税が発生する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告し、納付しなければなりません。これを怠ると無申告による加算税が発生する可能性があり、追徴課税されることもあるので注意が必要です。
次に、登記とは不動産などの所有権を公に証明するための手続きです。特に不動産の登記は所有権を明確にし、他者に対してその権利を主張するために欠かせません。贈与を受けた際には、その不動産の所有権が移転したことが第三者からみてもわかるように、適切に登記手続きを行います。
適切に登記手続きが行われないと、贈与税の申告や納付において問題が生じることがあります。また、登記がなされていない場合、財産の所有権を第三者に主張することができず、トラブルの原因となることもあります。
例えば贈与者が死亡した際に贈与の事実が不明であれば、贈与を受けたはずの人の財産ではなく、贈与者の相続財産として扱われる可能性があります。せっかく贈与をうけていたのに、登記をしていなかったということで贈与の事実がなくなってしまうわけです。これを避けるためには、きちんと登記を行うことが重要です。
親族間での贈与は、友人や知人と比べて信頼関係が築かれているため、問題が起こりにくいとされています。しかし、贈与を行う際には税金や法的手続きに留意しなければなりません。
贈与税が発生するかどうかは、贈与額によりますが、親族の場合には特例があるため、一定の額までは贈与税がかからないこともあります。贈与税を軽減するために毎年の基礎控除を利用し、定期的に少額ずつ贈与を行う方法もあります。この方法も注意は必要ですが。
相続時精算課税制度とは、相続が発生した際に贈与を受けた財産が相続財産として合算され、相続税が計算される制度です。この制度を利用することで、贈与を受ける側は贈与税を前倒しで支払い、相続時にはその分が相続税から除外されるメリットがあります。
この制度を利用するにはいくつかの条件があります。例えば贈与者が60歳以上で、贈与を受ける側が20歳以上であることが必要です。また課税の対象となる財産の総額には制限がありますので、事前に確認してください。
親族間の贈与でも、後のトラブルを避けるためには贈与契約書を作成しておくことが望ましいです。贈与があったことを証明するための重要な証拠となります。また、契約書を作成することで贈与の条件や額が明確になり、誤解によるいざこざを防ぐことができます。
契約書には、贈与者と受贈者の氏名、贈与する財産の詳細、贈与の意思表示があった事実など法律要件と法律効果といった法的な文言を記載します。
贈与の登記を依頼した司法書士にお願いすれば贈与契約書も作成してくれます。
贈与を行う際には、後の相続にどのような影響を与えるかを考慮する必要があります。贈与があった場合、その財産は相続財産から除外されますが、贈与が行われたのが相続直前であった場合、不当に財産を隠そうとしたと見なされて相続財産に加算される危険性があります。
また、相続分の調整を行うために贈与を行った場合も相続人間で争いを生む原因となることがあります。事前に相続人としっかりと話し合い、贈与の意図を明らかにすることが大切です。
親族間での贈与を円滑に行うためには、贈与税と登記手続きについて理解しておかなければなりません。関係者でしっかりコミュニケーションをとり、専門家の意見を聞きながら進めましょう。非課税枠を使って何年かに分けて贈与をしたり、相続時精算課税を使うことで、みんなにとって良い贈与になることが大切です。