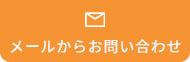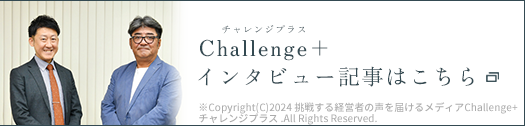成年後見申立て手続き
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の生活を支える重要な制度です。
この制度を利用することで、本人の権利・利益を守ることができます。たとえば、高齢者や障害を持つ方が、財産の管理や医療について適切な意思決定を行うことができるよう支援されます。
また、そのような方々を単に保護するだけでなく、本人が尊厳を持ち、可能な限り自立した生活を送れるようにするための支援も含まれています。後見人は、法律や金銭管理の知識を持つ専門家が務めることが多く、そのため安心してサポートを受けることができます。
ご家族で支えていきたい、という場合には親族が後見人となれるケースもあります。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は、裁判所によって後見人が指定される制度で、本人や法律で定められた申立人から裁判所に申立てがされます。一方、任意後見は将来の判断能力の低下に備えて本人が信頼できる人を後見人として指定し、あらかじめ契約を締結しておく制度です。任意後見は、本人が自らの意思で後見人を選ぶことができるという利点があります。
どちらの制度を選ぶかは、本人の状況やニーズに応じて判断する必要があります。法定後見は裁判所の手続きが必要となるため準備の手間や時間がかかりますが、任意後見はそこまでの手間や時間はかかりません。
また法定後見にも後見、保佐、補助という3つの類型があり、判断能力の程度に応じてどの類型になるかが決まりますが、これ以後は法定後見のことをひとくくりに成年後見と記載します。
【成年後見申立ての必要書類】
1. **成年後見申立書** 申立ての目的や理由を記載する書類です。専門的な法律用語が出てくることもあります。
2. **本人の戸籍謄本と住民票** 本人の身分証明のための書類です。
3.**後見人等候補者の住民票** 後見人等になろうとしている人の住民票です。
4. **医師の診断書** 判断能力が不十分であることを示すため、医師の診断書が必要です。
この診断書に基づいて3類型のどれに該当するか判断されます。
5. **その他の書類** 膨大な書類を作成する必要があります。その根拠となる資料も用意します。
原則的には申立人が上記の必要書類を揃えて裁判所に申立てを行います。しかしながら難易度が高いので、実際にはこの申立てにおいて司法書士が非常に重要な役割を果たします。申立て手続きに必要な書類の作成や提出、さらには裁判所での手続きを申立人に代わって行います。特に、法的な知識が必要な部分においては司法書士のサポートが不可欠です。
書類作成だけにとどまらす、本人の状況に応じた適切な後見の選択や、必要な手続きのスケジュール管理など、専門的な知識を活用したサポートもします。
【裁判所での成年後見申立て手続きの流れ】
1. **申立ての準備** 必要書類を集め、司法書士と打ち合わせを行います。
2. **申立ての提出** 作成した申立書と必要書類を、管轄の家庭裁判所に提出します。
3. **審判期日の指定** 裁判所が申立てを受理した後、審判期日が指定されます。
この際、必要に応じて、当事者や関係者の出席を求められることがあります。
4. **審判** 指定された期日に家庭裁判所で審判が行われ、後見人の選任が決定されます。審判内容については、裁判所から通知がきます。
5. **後見の開始** 審判が確定した後、正式に後見人の業務が開始されます。
成年後見の申立てに要する時間は、場合によって異なります。一般的には、申立てから審判までに数か月かかります。ただし、必要書類が整っているかどうかや、家庭裁判所の状況で変動するため、余裕を持った計画を立てることが重要です。
申立てにかかる費用として、司法書士への報酬や、申立て手数料が必要です。司法書士の報酬は、依頼内容や地域によって異なるため、事前に見積りをもらうようにしてください。
今回は申立て手続きにスポットをあてて紹介しましたが、これから申立てを検討する方にはまず、成年後見制度とはどういった制度であるか、任意後見にはどういった利点があるのかを知っていただき、本人のためにはどう制度を使ってどのように支援していくのが最適なのかを考える方が先かと思います。それについてはまた今後掲載していきたいと考えています。