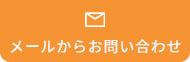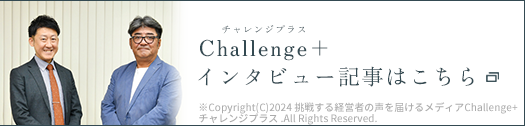役員変更登記
会社の役員に関してはその役員に関する情報を法務局に登記申請し、登記簿に反映させる必要があります。役員の氏名、役職、就任・退任日など、会社の経営に関連する重要な情報を外部に対して公示するものです。そしてその登記に変更が生じた際には役員変更登記をしなければなりません。きちんと変更登記をすることで会社内部の組織体制が正確に反映され、取引先や顧客からの信頼を得ることにつながります。会社の意思決定が誰によって行われるのかを明確にすることで、取引先や株主に対しても信頼性を確保できます。また破産や重篤な過失による懲戒処分を受けたなどの理由により役員の資格が失われる場合、迅速な変更登記をすることで周囲に悪影響を及ぼさないようにし、適切なガバナンスを確保することが可能となります。
株式会社においては、役員が退任する場合や新たに役員を選任する場合に必ず取締役会または株主総会での決議が必要です。この決議により役員の選任に対する合意が得られ、透明性を持った運営が実現します。
役員の変更にあたっては定款の変更が必要になる場合もあります。定款というのは株式会社の基本的なルールを定めた文書であり、会社設立時に必ず作成し、法務局に提出して会社設立登記を行います。その定款には会社の目的や事業内容、役員の選任、株主総会の開催方法など、会社運営に必要な基本情報が含まれています。定款を変更するためには、役員変更の決議と同様に株主総会での承認が必要となります。
また、株式会社については役員の任期が決められており、任期がが満了した際にも退任の登記をする必要があります。例えば取締役については「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。なんか難しい言い回しですが、おおよそ2年!と考えることにします。株式を公開している公開会社はこの任期を守らなければなりませんが、株式を公開していない非公開会社では定款で定めることによってこの2年を最大10年まで伸長することができます。ただし、必ず定款で定めておかなければなりません。
取締役会や株主総会での役員変更の決議が完了したら、役員変更の登記申請を行います。登記手続きには登記申請書、決議をした議事録、就任承諾書や辞任届などの書類が必要で、これらの書類が準備できたら法務局に申請します。申請が受理されると数日内に登記が完了し、情報が公示されることになります。
株式会社では通常は2年に一度は取締役変更決議、取締役変更登記をしなければなりません。定款で任期を伸ばしていても最低10年に一度はやる必要があります。仮に任期が満了した取締役がそのまま再度就任するとしても「重任登記」といって退任、就任の手続きが必要になります。この登記義務を果たしていないと外部からの信用を落とすばかりでなく、過料といって罰金を科せられることもありますのでご注意下さい。
持分会社の役員の変更手続きは株式会社とは異なります。持分会社とは出資者全員が会社の経営に関与する形態の会社であり、合名会社、合資会社、合同会社のことを指します。株式会社は株主の出資を基に運営されますが、出資者は経営に参画しません。いわゆる所有と経営の分離です。それに対して持分会社は出資者それぞれが持ち分に基づいて活動し、経営も行っていきます。持分会社は比較的簡便な手続きで運営できるため、フレキシブルな経営が可能であり、役員の変更に関する決議が法的に厳格に求められないといった性質があります。ただし出資者の合意を得ることは必須です。そのため持分会社においても役員の変更時には適切な手続きが求められます。
そして株式会社との大きな違いは任期の定めがないことです。役員の顔ぶれを変える必要がないのであれば役員変更決議、役員変更登記をする必要がなく、過料を科せられることはありません。
さて、ここまで役員変更の手続きについてお話してきましたが、どのように手続きを進めればいいのか?
費用は発生しますが、会社の登記のプロである司法書士に依頼して下さい。
経営者の方がご自分でされることもありますが、場合によってはかなり苦労しますし時間がかかります。会社運営のための時間を確保しつつ、手続きをスムーズかつ正確に進めるため専門家に丸投げすることをおすすめします。